2
管理・運営支援
(Management and operation support)
建築資産運用においては日々の施設環境を充実させ、資産価値を最大限に
活かすことが重要です。
建物の維持・管理・修繕や運営に関する
個別のニーズを把握し、
「安心・安全・快適・清潔」な
施設環境を実現するソリューションを
提供します。
LCCO2の検証、建物の長寿命化、
エネルギー消費削減の提案や、
エンジニヤリングレポートの作成、
時代と共に変化する利用者の新たなる
ニーズに対応した更新・改修計画を
提案いたします。
エネルギー診断
(Energy Diagnosis)
企業の事業継続計画への取組みと併せて、地域全体への貢献も視野に入れて対策を行う企業も増えています。
特に地域との関連性が高い企業は、BCPだけでなくDCP(District Continuity Plan)地域継続計画の策定も進めています。
災害時に、地域住民を工場などの企業施設へ受け入れ、自社で用意しておいた電力インフラを提供する体制を整えているのです。
地域との結びつきが強い企業にとっては、DCPも BCP対策 の一環であると言えます。
通信手段を維持するためには、パソコンやスマホを1週間ほど維持できる予備電源の確保も必要になります。
記憶に新しい大阪北部地震においては、災害時無料Wi-Fi「00000JAPAN」が提供され、インターネットでのやり取りが可能になりました。
このように安否確認や取引先への連絡手段として、インターネットによる通信が確保できる可能性が高いと言えます。
あとは使用するパソコンやスマホの電源確保が重要になってくるのです。
診断の重要性
基本的に建物診断・劣化診断は、施設全体の劣化や不具合の状況を把握し、その劣化や不具合に対して、適切な修繕方法や予算を策定する目的で行います。各種施設の快適な環境や資産価値の維持・向上を図るためには、建物診断・劣化診断で現状を把握したうえで、適切な修繕計画を立てることが重要です。
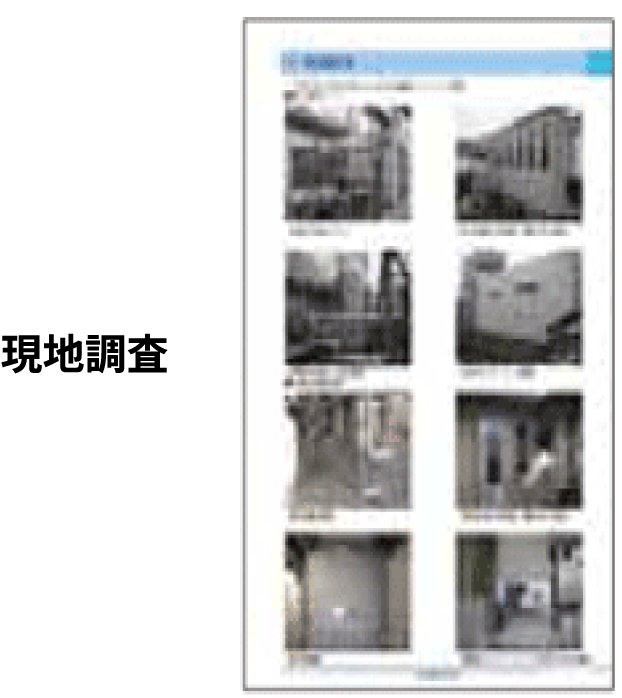
建築設備はいかに保守管理を徹底しても、経年により劣化が進みます。機器類については一般的には15年から20年程度、配線配管類は40年前後といわれており、建築物に比べ耐用年数は短く、そのため、更新等のサイクルも早く、必要に応じた対応が必要になってきます。
また、建物の利用者及び周辺を含む第三者の生命と財産を安全に確保するためにも重要で、建築設備の維持保全を行うことは不可欠のものであります。
そのため、建築設備の維持保全を行うことは各種の法律でも義務付けられており、相応の時期に修繕や改修を実施することは資産価値の保持や向上、投資の合理化につながります。
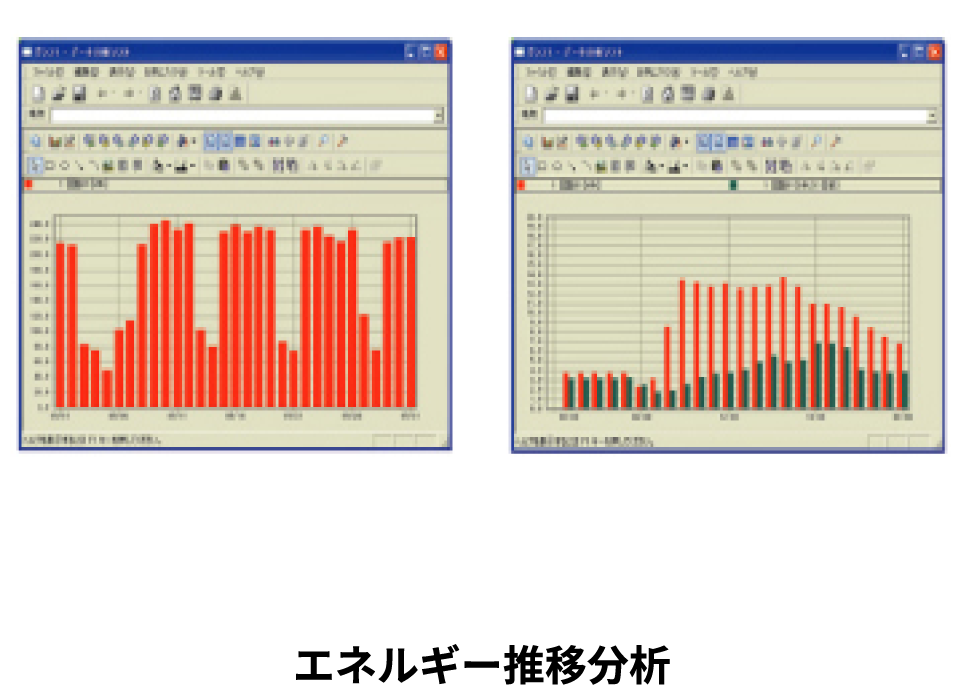
大企業等の多くでは、基本的な取り組みとして、自社の経営課題と省エネを関連付けて、経営課題には環境配慮といった環境経営の視点を取り入れ、本業と省エネの両立を図る事例や省エネを企業ブランドの向上に活用する事例等が見られています。
中小企業等においては、経営者の省エネ意識を向上させることを目的とした省エネに関するガイドラインがあることが省エネ化には必要です。
ガイドラインには経営にどのように省エネを取り入れるかの視点から、省エネのメリットや省エネ推進のために実施すべき事項(目標・方針の設定、体制整備、エネルギー等の使用状況の把握、等)が盛り込まれることも必要です。
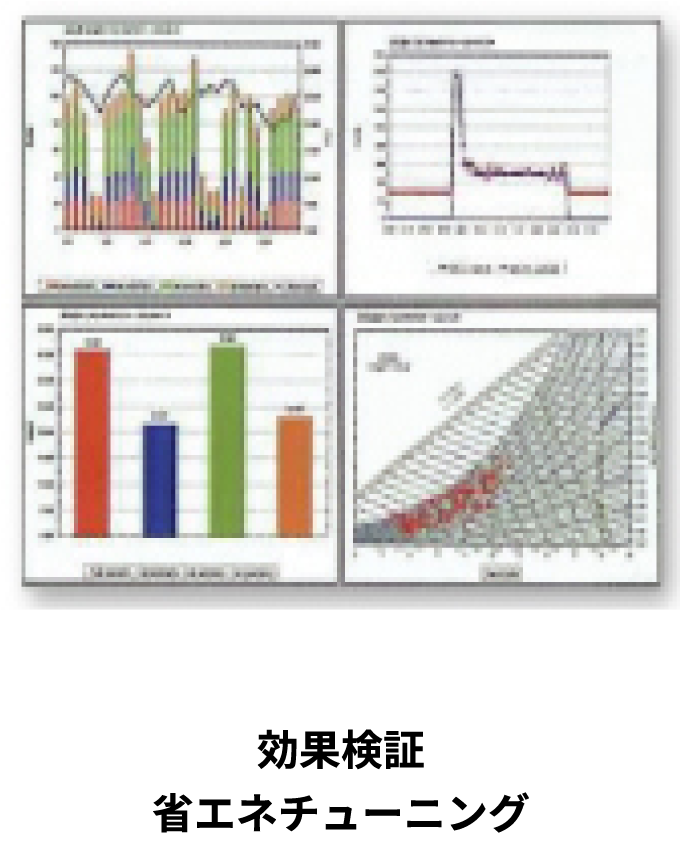
受け手の能力・関心に合わせた提案や診断後のフォローアップの必要性も示唆されています。
どのような省エネ対策があるのか解らないという情報不足バリア、有効な省エネ対策を検索するために必要な時間と費用という隠れた費用バリア、時間等の制約により現場の担当者が最適な省エネ対策を実施できない限定合理性バリア等の優先的解消が、省エネへの意識変換効果があると考えています。

お問い合わせ
- TEL03-6215-8429
- メールにてお問い合わせ
