1
環境設備設計・省エネルギー・脱炭素デザイン
(Environmental equipment design / energy saving design)
ITの普及により、遠隔地の人同士で仕事を行うことができるようになった現在、
機械設備(空調・換気設備、給排水衛生設備)、
電気設備、IT、IOT、など様々なエキスパートによるアライアンス(連合組織)を編成し、業務を遂行していきます。
環境性、機能性、快適性、安全性、経済性に優れ「地球温暖化対策」も考慮した、総合的に品質の高い設備環境の実現
を追求します。
ESCO事業が持つ現状の課題
まず最初の課題は、その事業を行うための削減額保証のリスク感の大きさです。
通年来ESCO事業は補助金を得て行う為、 必然的に3年間に渡り、国に対しての効果検証保証業務が義務付けられていて、3年間提案通りの内容をクリヤーできていれば、残契約保証期間の保証はクリヤーされているのが現状で、リスク感は案外大きくないものです。

次に近年では多くの企業がIT化と共にESGを意識した経営手法を採用している為、環境(Environment)では二酸化炭素の排出量削減や化学物質の管理、社会(Social)では人権問題への対応や地域社会での貢献活動、企業統治(Governance)ではコンプライアンスのあり方、社外取締役の独立性、情報開示などを重視する傾向があります。
企業のESGを含むエコ活動として「パリ協定」に準拠した様々な「温暖化防止テーマ」が掲げられており、ESCO事業提案内容との整合性が重要視される場面も多くなってきていることが挙げられます。
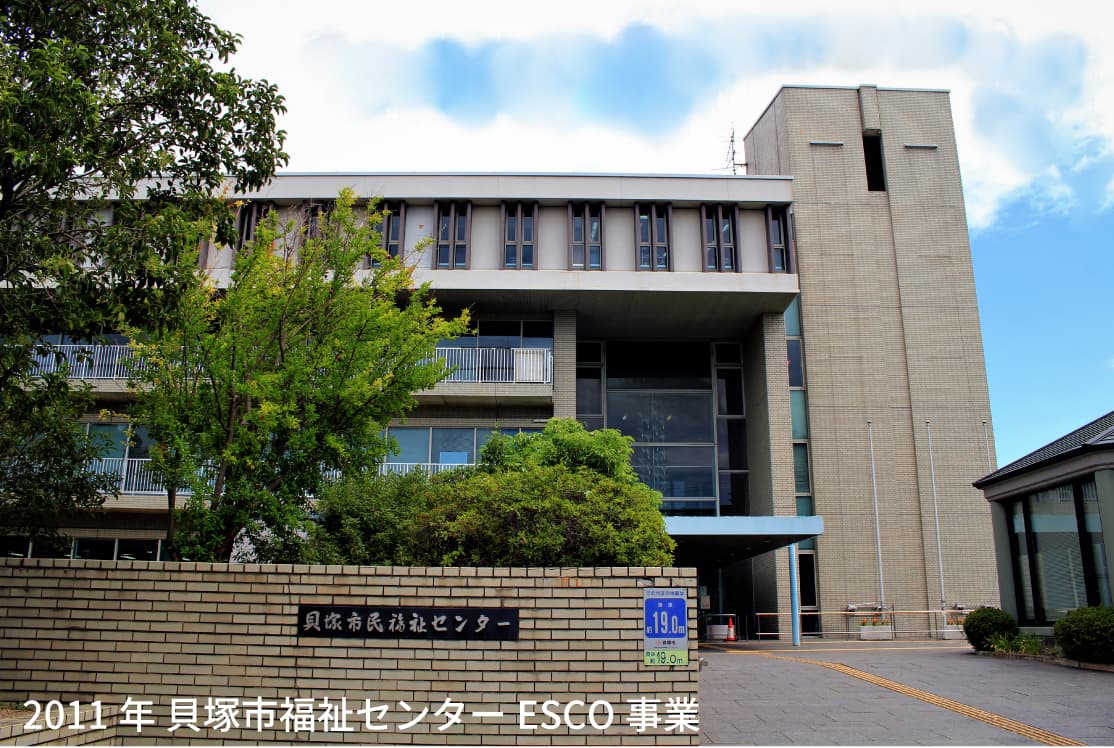
それらの企業は、ESCO事業をエネルギー費の削減額で賄う事のほか、さらなる利益を上げる1つの手段として考えているケースが少なくありません。
さらなる利益とは、サプライチェーンを含めた温暖化問題への意識改革の提案や、ESG投資への推進効果提案などをESCO事業の中に求めています。

ESCO事業者側から考えてみますと、ESCO事業が効率的に実現されるためのポイントは、社会的に非常に有意義である事業でありながら、その事業を行うことで利益を得ることができることです。
ただし一般的に利益と言うと金銭的なものを指す場合が多いのですが、最近のESCO事業ではそれだけではなく、様々な面での総合的な利益を得ることを目的としないと、省エネ・省コストだけの提案では契約まで至らない場合が多くなってしまうので注意が必要です。
例えば顧客がESG投資を期待している企業の場合には、ESCO事業が行われた場合、その効果が様々なところで取り上げられることによる広告宣伝効果や、ESCOイメージの向上によるESCO事業者に対するイメージアップなどが容易に行われ、その面では高額な広告宣伝費を出費するよりもはるかに効率の良い事業となることも多いものです。

日本は2016年約0.5兆ドルから2018年には約2.2兆ドルへ約4.6倍と、直近のESG投資の拡大は目を見張るものがあり、投資残高では約7%と欧米には 及ばないものの、欧州、米国に次ぐ3番目に大きな市場として存在感を増しています。
世界のESG投資残高は2016年の約22.9兆ドルから2018年には約30.7兆ドルとなり、この2年間で34%増と大幅に増加した。そして、2020年には35兆ドルに達すると見込まれています。

一方国内のESCO事業は2013年以降年間100〜150億円前後で推移しています。
ESCO事業が伸びない理由の一つに地方自治体の公募の減少が挙げられています。
ただし公募しても応募事業者が少ないこともその原因になっています。
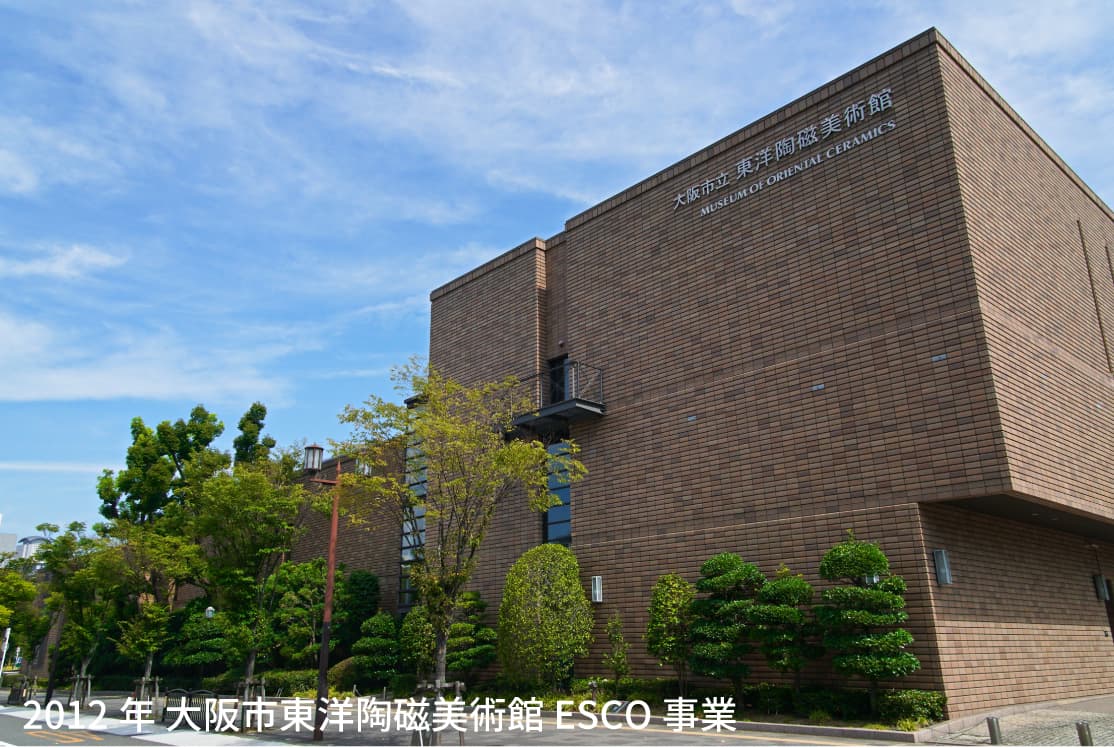
ESCO事業により設置された省エネ設備については、これを顧客の所有とせず、名目的にESCO事業者ないしリース業者の所有とすることで、顧客の資産の外部化 (オフバランス化) が図られるとし、かつてはこれがESCO事業のメリットの一つであると説明されることがあリました。
しかし国際会計基準への整合を図るべくリース取引に関する会計基準が改正され、2008年4月以降、すべてのファイナンス・リース取引に係るオフバランス処理が認められないことになりました。
それとは別に、特に中小の事業者や地方の地元設備工事店はリース契約の与信が大きな壁になって公募型ESCO事業への参加を拒んでいます。

そこで「代理受領」を利用することをご検討いただきたい。
⾦融会社がESCO事業者から、お客様に対する「ESCOサービス料」の集⾦業務委任を受け、お客様から受領した「ESCOサービス料」の内「⼯事元⾦分+利息+固定資産税」を⾃⼰債権の弁済に充当し「残ったサービス料をESCO事業者に⽀払う」流れを「代理受領」と⾔います。
これを利用することで、中小事業者でも自治体の公募案件に安心して応募ができるのです。
図で説明しますと次のようになります。


建築主は、設備の初期投資やシステムの
運用に伴い発生する
様々なリスクを回避することができ、
省エネ、省コストが事業者の支援によって実現できます。
以降の設備管理の方法としては、
日常管理は建築主が行う場合、
すべての管理を事業者に任せる場合など、
相互の取り決めによって様々な運営方法があります。
お問い合わせ
- TEL03-6215-8429
- メールにてお問い合わせ
